イベントレポート
2012年12月13日 (木) 19:00~21:00
米田 智彦(よねだ ともひこ) / フリーエディター
個人の生き方を切り拓く
デジタルの可能性
Blog、Facebook、Twitter・・・。 ソーシャルツールを持つことが当たり前 となった今、その使い方は個人に委ねら れ、ビジネスや日常生活などさまざまな シーンでのコミュニケーションの仕方は 変化の時期を迎えた。 今回は、2011年に家と家財を捨て、東京 を旅して暮らす「ノマド・トーキョー」を約1 年間実践・発信し、NOMADライフの先駆 者としてその先の新しいライフスタイルを 探求しているフリーエディターの米田智 彦氏に、"個人"としてのワークスタイル や情報発信の在り方、さらにはインフラと してのデジタルのこれからについて語っていただきます。
ソーシャルメディアの可能性を探った『ノマド・トーキョー』

ソーシャルツールを利用して個人が情報を発信する。双方向でやりとりをする。そこから生まれる新しいライフスタイル。こうしたデジタルの可能性をさまざまな活動を通して追求してきたのが本日の講師である米田智彦氏だ。セミナーでは紙媒体からデジタルまでをカバーする編集者としての米田氏の仕事、話題となった生活実験『ノマド・トーキョー』、ソーシャルツールがもたらした社会の変化などについてお話しいただいた。
米田氏は1973年生まれの「テレビ世代」。自身を「70年代、80年代のアニメとバラエティーで育った人間です」と振りかえる。長じては出版社に就職、2006年にフリーランスとなるまでは雑誌の編集やデジタル関連事業など「アナログとデジタルの境目」で仕事をしてきた。時代はちょうどインターネットが普及し、iモードが登場したころ。それまでマスメディアが占有していた情報発信が個人でも可能になりつつあった時代だ。これによって米田氏の仕事も「在り方が大きく変わった」という。独立後はさらにその動きが加速。ツイッターなど世に出たばかりのソーシャルツールを駆使して企業の広告キャンペーンを展開したり、日本初となるユーストリームの本を刊行するなど、変化の激しいデジタルの世界を開拓者として走りつづけてきた。
そのなかで、2011年に「突然始めた」のが、家も家財も捨て、約1年をかけて東京を旅するという『ノマド・トーキョー』だった。
「家もオフィスもなくし、ソーシャルメディアの伝手だけを辿ってどこまでできるか、やってみようと思ったんです。」
目的はそれだけではない。東京という都市への興味もあった。
「東京は巨大な都市なのに、知っているのは自分の家や職場のあるところくらい。もっと知らない町を見たかった。この都市の恵みをシェアし、享受してみたかったんです」
「旅」で感じたこと、わかったこと
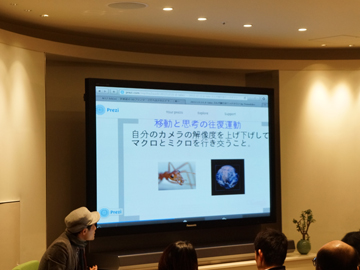
スタートは2011年1月11日。ツイッター上で「家をなくしてみました。誰か泊めてくれませんか」と「一方的に宣言」してみた。
グーグルマップと連動させ、見れば自分が今現在どこにいるかがわかる「米田マップ」も作成した。リアルタイムの情報発信は「予期せぬこと」を次々と呼んだ。「うちでよければ」と宿泊先を提供してくれる人たちが現われた。カフェで仕事をしていたら「隣の席の者ですが」とリプライされたこともあった。11カ月の「旅」の間は「ノマドワーカー」として仕事をこなしながら、西は青梅市から東は墨田区まで約30カ所を渡り歩いた。ホテルにもよく泊まった。見知らぬ町で迎える朝は、その町の素顔が見えるようで新鮮だった。生活は「移動と思考の往復運動」。いままでにない視点を得ることができたし、「物の所有や消費」といったものを深く考える機会にもなった。
学生時代はバックパッカーとして海外を放浪した米田氏。旅はまた、自分の中にあった「本能」を呼び起こしてくれたという。
ここでパネルに表示されたのはアメリカの心理学者マズローの唱えた「欲求5段階説」。
「生存欲求」「安全の欲求」「社会的欲求」「自我の欲求」「自己実現の欲求」の5つに分かれた人間の欲求のうち、米田氏がこの「旅」の間に感じたのは主に「生存欲求」と「自己実現の欲求」の2つだった。これが示唆するように「ノマド=遊牧民」の生活は「人生をシンプル」にすることでもあった。
「実はそれまでの3年間はソーシャル漬け。ツイッターやフェイスブックが生活のすべてになると、本当はリアルな生活があるのに、ソーシャル上で起きた些細なことがリアルの世界で起こったかのように思ってしまう。だから、『ノマド・トーキョー』はそういう意味で人生を再復活させる、ある種のショック療法といった感じのものでもあったんです。」
ノマドの生活に限らず、移動にはさまざまな効用がある。米田氏の場合は移動しているときに「いろんなアイデアが湧く」という。ネットの口コミ情報ではない自分の足で稼ぐ一次情報は「自分の言葉」であり「オリジナリティー」だ。『ノマド・トーキョー』では「自作自演を照れず」に「自分自身をメディア化」したことで新しい出会いに恵まれた。年下の若い友人もたくさんできた。
「ツイッターで呟くときによく思うのは、俺はどれだけ俺が好きなんだろうということですね。でもインプットしなければアウトプットはないんです。」
ソーシャルメディアは関心を同じくする人と知りあう機会が多い場だ。そこにリアルの行動が伴うと、いわゆる「セレンディビティ」と呼ばれる能力が身につき、「偶然の中の幸運」を見つけやすい体質になるという。米田氏はそれを『ノマド・トーキョー』で体現してみせた。ネット=情報空間とリアル=物理空間、この2つをバランスよく往復することがデジタルの時代を生きる術なのだ。
ソーシャルツールは「ただの道具」

セミナー後半の1時間は質疑応答の形をとりながらのフリートーク。ここで話題となったのは「地縁社会」。米田氏の答えは「地縁社会はあった方がいい」。ソーシャルメディアは崩れかけていると言われている地縁社会を、デジタルでつくられたリアルな人間関係によって支えることができるのではないかというのが米田氏の考えだ。
会場の全員が思わず我が身のことと苦笑したのが、「フェイスブックは世界が広がるけれど、時間がとられる」という意見。これには米田氏も「僕もツイッターに嵌ったときは起きてから寝るまで一日中ツイッターをやっている状態でした」と返答。解決策は「チェックするのは空き時間だけ」、「自分基準でしか見ない」という具合に「自分でルールを決めること」。訴えたいのは、結局のところソーシャルツールといえど「ただの道具」に過ぎないということだ。
「道具だから使いたおせばいい。新しいものが出たら使い方を覚えるだけのことです」
もちろん、これ以上はなく便利な道具であるのもデジタルツールだ。
「放浪してわかったのは、サバイバルなところでもインターネットは役立つということ。仕事や生活、個人の人生に関わるデジタルの使い方をこれからも研究していきたいですね。」
そう語る米田氏の「夢」は「近いものとしては、今書いている本の執筆を無事終えること」だ。『ノマド・トーキョー』を含むここ数年のソーシャルを巡る旅を描いた新刊は2013年春に刊行される予定だ。
講師紹介

- 米田 智彦(よねだ ともひこ)
- フリーエディター
出版社、ITベンチャー勤務を経て独立。現在はフリーの編集者・ディレクター・ライターとしてアウト プットに囚われず、企画・編集・執筆・制作・モデレートを行っている。2005年よりCMプランナー・有 志とともに、“東京発、未来を面白くする100人”をコンセプトにしたインタビューWebマガジン 「TOKYO SOURCE」を立ち上げ、2008年、TOKYO SOURCEでの活動をまとめた、第一弾書籍 『これからを面白くしそうな31人に会いに行った。』をピエブックスより出版。近年は企業と組んで、プ ロダクトやソフトウェアのコンセプトワークやコピーライティング、ソーシャルメディアを使った広告キャ ンペーンのディレクション・ライティング、出版プロデュース、イベントや教育事業の企画・モデレー ターも務め、編集行為を拡張している。
「ノマド・トーキョー」URL:http://ustre.am/LVMX
メールマガジン「トーキョー遊動日記」URL:http://ustre.am/LVMX


