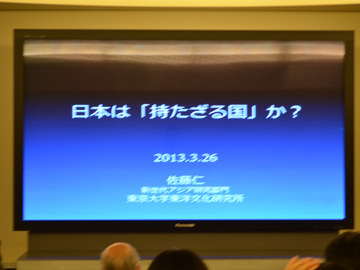イベントレポート
2013年3月26日(火) 19:00~21:00
佐藤 仁(さとう じん) / 東京大学東洋文化研究所 准教授
日本は「持たざる国」か?
日本は「持たざる国である」という先入観の歴史は古い。いま話題になっている原発依存も、1970年代のオイルショックを契機とした「持たざる国」の脅迫観念に後押しされてきた。他方、ほとんど知られていないのは、「持たざる国」の固定観念が作り出された虚構であり、海外進出よりも国内資源の開発を主張していた論者が戦前から存在したことである。彼らのアイデアはなぜ不発に終わり、日本はなぜフクシマへの道を歩むことになったのか。ここには、単なる数字合わせのエネルギー論を超えた、知の縦割り構造という根深い問題が横たわっている。忘れられた資源論を思い出しながら、いまの日本で必要な国土との向き合い方、そしてそれを下支えする知のあり方を考えてみてはいかがだろう。
日本は「持たざる国」?それとも「持てる国」?

資源とは何だろうか。一般の人間が頭に浮かべるのは石油や石炭、天然ガスといった化石燃料や金属などの鉱物資源だろう。講師の佐藤仁氏が最初に見せてくれたのは一枚の騙し絵。見方によっては若い女性にも老婆にも見えるこの絵は、若い女性ばかり見ていると老婆が見えなくなり、老婆ばかり見ていると若い女性が見えなくなるという特性がある。
「これからお話する資源の話はまさにこういう話です。」
日本は「持たざる国」というのが常識。だが見方を変えれば「持てる国」になるかもしれない。セミナーはまず「日本には資源がない」という常識を頭から取り払うところからスタート。前半は戦前戦後の資源に対する国家としての日本の考え方や実際にとってきた行動、後半は現代の日本社会が抱える問題について考えるものとなった。
大学では資源政策論や環境政治学などを教えている佐藤氏。研究者としてはタイ西部の少数民族の村などを舞台に森林保全や土地の問題などをフィールドワークしてきた。そこで感じたのが資源の一体性。行政は森林局、河川局といった具合に環境を分断して管理するが、実際にそこに暮らす人たちは、例えば「森の動物は森で狩らずに畑に現われたところで獲る」といったように、そうした階層とは関係のない一体的な世界で生きている。佐藤氏はこうしたところから「資源」というものに着目し、日本の資源について研究を進めるようになったという。
「持たざる国」の概念が主流だった戦前の日本

最初に調べたのは「資源」という言葉の由来。実は「資源」という言葉が一般化したのは昭和に入ってからのこと。それ以前、大正や明治時代は「資源」の語源である“Resource“は「助けとなるもの」「よりすがり」「富源」などと訳されてきた。佐藤氏が「素晴らしい」と紹介したのは1931年発行の『大英和辞典』にある「力を借りるもの」という訳。同時代の経済地理学者E・ジンマーマンは「資源とは、あるものではなく、『なる』ものである。」と説いている。それを資源と見なすかどうかは人間や時代が決める。石油もかつては存在自体は知られていたが「資源」とは見なされていなかった。同じようにかつては有用な資源とされていた石炭は現代の日本では放棄されて資源ではなくなった。資源とは、物と人間がセットになって初めて力を発揮するものなのである。
「ただやはり、世間一般から見たら資源は物、原料なんですね。」
石油がないから「日本は持たざる国」。こうした概念は戦前戦後を通じてこの国の主流的な考えとなってきた。ちなみに「持てる国と持たざる国」というのは日中戦争が起きた昭和12年の流行語。「資源」という言葉はその10年前の昭和2年に設立された「内閣資源局」(後の企画院)によって一般化された。内務官僚の松井春生が唱えたこの組織はいわば国力(資源)を集中して総力戦に打ち勝つことを目的としたもの。こんなふうに戦前の日本は欧米列強との競争に勝つために物であるところの資源を得ようと海外に進出し、最終的には第二次世界大戦に敗れることになる。
「一方でそうではない立派な意見もあったんです。」
例えば慶応大学の地理学者・小島栄次は「遥かに貧しい真に持たぬ国々が特に不満を主張せぬに拘らず、強国は盛んに不満を鳴らし」といった観察をしている。政治家の石橋湛山は日本が貧乏なのは「天恵が足りぬからではなくして、人工(工夫)が足りぬからである」と語っている。100年近くも昔の大正8年の帝国議会では伊澤多喜男が「天然の資源を保存するということは非常に大切なること」と、現代の環境問題を先取りするような発言し、内治における資源の保存を提唱する。しかし、今日も根強くあるように、技術的楽観論の方が優勢であった。この時代の総理大臣であった原敬は、たとえ資源を採り尽くしても「必ずしや人間の智慧では之に代る物を発見する」と技術の進歩に期待を寄せている。結局、日本は内治の充実ではなく、資源を外へ獲りにいく戦いに敗れて戦後を迎える。
資源とは「天然」「物的」と「人的」「知的」が合体したもの

戦後の日本の資源政策はどうなったか。それに大きな影響を与えたのがハーバード大学の地理学者・アッカーマン博士だ。博士は日本人の厳しい生活環境を目の当たりにし、資源調査会という組織を日本政府につくるよう提案する。少ない資源をトータルで有効利用しようという考えは学校教育の場にまで浸透し、その後の日本は1963年に輸入との比率が逆転するまでは高いエネルギー自給率を保つことになる。しかし石炭から石油への転換もあり、いまや天然資源の大半は海外に依存。これが日本の現状だ。
「では日本に資源がなくなったのか。国内で見ればなくなっているのは物よりもむしろ人。今日は過疎と教育、この2つの視点で見ていきたいと思います。」
セミナーの1週間ほど前に三重県の熊野市を視察してきたという佐藤氏。そこで見たのは過疎化の実態だった。耕作地は放棄され、いまやそれは社会問題化しているという。これは熊野だけの問題ではない。森林にしても日本は国土に対する森林面積が世界第3位でありながら利用率となると約40パーセントとけっして高くはない。「林業は儲からない」から人々は山から離れる。農業も漁業も過疎化でそれに従事している人は減る一方。第一次産業だけ見ても日本の資源は危機に貧している。
資源とは「天然」「物的」と「人的」「知的」が合体したもの。資源は「物」がそこにあるだけでは資源とはならない。それを「資源」に変えるには人の手や工夫が必要だ。
「このままでは日本は本当に持たざる国になってしまう。それが心配です。」
セミナーの最後に佐藤氏が引用したのは夏目漱石の『三四郎』の一節。
「熊本より東京は広い。東京より日本は広い。…日本よりも頭の中の方が広いでしょう。」
顧みれば、日本人は頭の中の広さを活用して豊かになってきた。とくに危機に瀕したときは力を発揮してきた。東日本大震災とそれにともなう原発事故に見舞われた現在の日本はまさにその危機にある。危機は見方によれば転換のチャンスでもある。今だからこそこれまでにはない価値観の多様化とそれを生み出す教育が何よりも大切だと佐藤氏は訴える。
佐藤氏の今後の夢、それは「実践」だ。
「価値観の多様化を促進するための教育に携わりたい。元気な人たちを集めてNPOのようなものを立ち上げ、人材を輩出したいですね。」
「持てる国」と「持たざる国」。その違いは「若い女性」と「老婆」が同時に見えるといった、多様な価値観をもつ人材の多さなのかもしれない。
講師紹介

- 佐藤 仁(さとう じん)
- 東京大学東洋文化研究所 准教授
1968年生まれ。主な関心は、天然資源の支配をめぐる国家と社会の関係。タイやカンボジアなど東南アジアでのフィールドワークを重ねている。主著に『「持たざる国」の資源論―持続可能な国土ともうひとつの知』(2011年、東京大学出版会)、『稀少資源のポリティクス―タイ農村にみる開発と環境のはざま』(2002年、東京大学出版会)などがある。