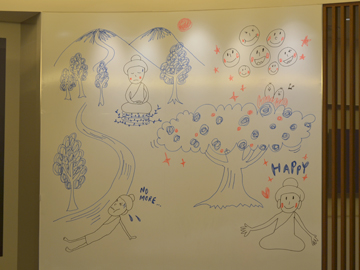イベントレポート
2013年8月27日(火)19:00~21:00
廣瀬 郁実(ひろせ いくみ) /
たのしいブッダと仏像入門
大切なのは生きること!
今から約2500年前に生きていたブッダが、生涯をかけて伝えたのは「ちゃんと生きよう」という知恵でした。そんなブッダがモデルとなってつくられた仏像。もとはブッダの像でしたが、わたしたち人間の願いによっていろんな種類の仏像が生まれました。ここ日本にも、人々の手によって大切に守られてきた仏像が数え切れないほど存在します。「生きる」というブッダの教えをベースに、いろんな仏像に出会ってきた廣瀬氏に、そこに込められた意味やメッセージを解説いただきました。
仏像のもとは2500年前に生きた一人の人間

釈迦如来に観音菩薩……仏像にはたくさんの種類がある。けれどそれについて詳しく知ろうとすると、何だか難しそうな気がする。そんな仏像のイメージを覆し、わかりやすい言葉で伝えてくれるのが廣瀬郁実氏だ。
「実は仏像というのはブッダという一人の人間がもとになっています。」
ブッダとは「悟りを開いた者」の意味。日本ではお釈迦様ともよく呼ばれる。
「日本人からすればはるか雲の上の神様みたいな存在ですが、ブッダも私たちと同じ一人の人間です。2500年前にネパールで生まれてインドで生きたゴータマ・シッダールタという男性です。」
セミナー前半では、そのブッダの生涯を辿りながら、彼が「仏像」となっていく過程を解説。廣瀬氏の話はブッダが「少年ブッダ」だったころからスタートした。
少年期のブッダは釈迦族の王子として城の中で暮らしていた。着る物にも食べ物にも不自由しない生活。だが、生まれてすぐに母親を亡くしていたため、その心にはどこか悲しみを抱えていた。王子であるがゆえ城壁の外に出ることは許されず「もやもやした毎日」を過ごしていたという。自分がいるこの世界は本当の世界ではない。一度でいいから外の世界を見てみたい。そう願った少年ブッダは、やがてたった1日だけだがそれを許されることとなる。
初めて目にする人々の暮らし。しかしそこにあったのは病や死、貧しさなどから日々生きることにすら苦しんでいる人々の悲しい生活だった。「こんなはずではない」とショックを受けた少年は、「きっとみんなが幸せになれる道があるはずだ」と考えるようになる。
「そして29歳のときに、ブッダは守られた世界から飛び出て、その道をさがしに出ます。これを〈出家〉といいます。」
「もう一度ブッダに会いたい」。人々の願いから生まれた仏像

出家したブッダは山に籠り、肉体を酷使する苦行を重ねる。だがいくら辛い修行を行なっても心はすっきりとはしない。自分の肉体的限界に挑戦することがはたして人々の幸せにつながるのだろうか。6年後、ブッダは違うと答えを出し、山を下りる。
「そのときのブッダはあばら骨が浮いてへろへろ。杖をついて山を下りますが、下り切ったときには精魂尽き果ててバタッと倒れてしまいました。」
そこに現われたのがスジャータというやさしい娘。乳粥を与えてもらったブッダは元気になり、枝振りの見事な大木(菩提樹)の下に座って瞑想を始める。そうしてはじめて、大地のぬくもりやキラキラした木漏れ日、鳥のさえずりや気持ちのいい風を感じ、「自分が生きていること=幸せ」を実感する。
「ブッダは『そうか、これが何よりも大切なことなんだ』と気がつきました。自分というこの命をただ息をしてすこやかに生きる。これこそすべての人が幸せに生きることのできる道なんだ、と。これが〈悟り〉です。」
悟ったブッダだったが自分の悟りがあまりにシンプルすぎて人々には届かないだろうとあきらめかけた。が、そこに神様である梵天が現われ、「勇気を持って伝えよ」と告げる。決意したブッダは、以後、80歳で世を去るまで旅をつづけ、生涯をかけて自分の教えを人々に伝えつづける。その教えとは「生きる」。ひとつしかない自分の命をちゃんと生きる。人々はその教えに感動し、ブッダに深く帰依する。人々にとってブッダはキラキラと輝く眩い存在。そばにいられるだけで自分を元気にしてくれる、そうした「お日様のような」存在となってゆく。
「ただ、ブッダはそれを見てまずいぞとも思うようになるんです。」
人々は光を与えてくれるブッダに自分もお返しがしたいと身の回りの世話をしたがったり、食べ物を捧げたりするようになっていた。誰かをあがめて奉仕するというのは「あなた自身を生きなさい」という自分の教えとは違う。そこにブッダは不安を抱く。
「ブッダは死ぬ前に、自分の像はけっしてつくってはいけないと何度も言いました。」
自分を神のように崇めてはいけない。誰かのために生きたり、依存してはいけない。ところが、その遺言は破られることになる。
「ブッダがいなくなって人々は少しずつ苦しい毎日に戻っていってしまいます。ブッダにもう一度会いたい。ついにはその気持ちが勝って、仏像をつくることになったんです。」
仏像は心で感じるもの

ブッダの偉大さを表現しようとつくられた像には、人間にはない色んな特徴が生まれた。「ぐりぐりとした」螺髪(らほつ)とその上の肉髻(にっけい)、額の百毫(びゃくごう)。手には「人々をもらさず救う」ための水かきがある。肉づきはふっくらとし、足は大きく、その身体は金色に輝いている。こういった姿は「如来」と呼ばれ、「正しい道を示す」という役割を示している。一般に人々がイメージする仏像とはその多くがこの如来の像である。奈良や鎌倉の大仏もこれに当たる。
こうして生まれた仏像は、人々の願いが細分化するにつれ種類を増やしていく。日本にもよくある観音菩薩像に代表される「菩薩」は「悟り」以前の若いブッダの姿がモデルだ。薬師如来は病を治したいという願いから生まれたもの。ブッダが生まれたときの姿を現わした誕生仏。苦行直後の出山釈迦像。「お地蔵さん」は地蔵菩薩であり、他にもヒンドゥー教の神々が仏教に取り入れられてできた梵天や帝釈天、吉祥天、弁財天などの仏像がつくられることとなる。
セミナーのラストでは、小学生が木の実でつくった薬師如来像や、中学生が彫ったお地蔵さんを紹介。「子どもたちが心をこめて一生懸命つくった立派な仏像です」と廣瀬氏。
廣瀬氏自身が仏像と出会うきっかけとなったのは「中学生のときに大好きだった父が亡くなった」こと。死について考えるようになったとき、出会ったのが三十三間堂の仏像だった。静かにたたずむ仏像と向き合ったときに覚えたのは「感動」だった。
「『今』だけをみたらどんな人もしあわせなはずです。生きているんだから。」未来に向かって無理に「夢」を追うことはないという廣瀬氏。伝えたいのはただひとつ、「ただ、生きる」ことだ。
「同じ人間の先輩であるブッダのように、私たちもたった一人の「自分」をちゃんと生きる。それがなによりも大切なことです。でも、迷ったり悩んでしまうのも人間。そんなときはふらっと仏像に会いにいってみると、元気や勇気をもらえるはずです。」
「自分らしさ」を応援するd-laboにふさわしい、廣瀬氏のメッセージに会場から大きな拍手が送られ、セミナーは幕を閉じた。
講師紹介

- 廣瀬 郁実(ひろせ いくみ)
-
上智大学比較文化学部日本語日本文化学科卒業(日本美術専攻)。小さな頃の父の死をきっかけに仏像と出会い、2007年から5年にわたり「仏像ガール®」として、仏さまの魅力、それを守り伝えてきた人間のチカラなどについて全国各地での講演やメディア・執筆活動を行う。2009年からの2年間は奈良国立博物館の文化大使も務めた。現在は、仏像だけでなく海外や日本全国の旅、山など自然の中での経験・生活を通して気づいた「元気に生きるヒント」を伝えている。著書に「感じる・調べる・もっと近づく仏像の本」、「でかける・感じる・きっと出会える仏像の旅」(山と渓谷社)がある。廣瀬郁実 自然と共に生きよう