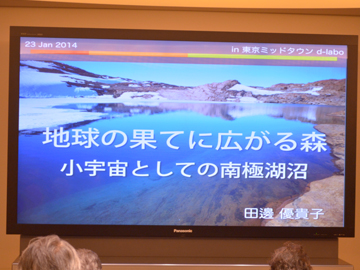イベントレポート
2014年1月23日(木)19:00~21:00
田邊 優貴子(たなべ ゆきこ) / 早稲田大学 高等研究所 助教
地球の果てに広がる森、小宇宙としての南極湖沼
私たちが暮らす日本からはるか遠く離れた南極大陸。そこは雪と氷に閉ざされた極寒の世界?実は南極大陸の縁辺部には氷に覆われていない岩肌が剥き出しの場所があり、そこには真冬になっても凍らない、一年中、水をたたえた湖が数多く存在します。湖の中に潜ってみると、湖底一面がまるで草原か森林のように緑で覆われた世界。人類が唯一、棲みつくことが出来なかった大陸・南極は一体どのような世界なのか。いま、極地ではどんなことが起きているのか。そして田邊氏はなぜそのような場所で研究をしているのか。地球がそのまま見える場所・南極の自然と生き物、湖底に広がる森の不思議な世界を、日本南極地域観測隊に3度参加した気鋭の研究者・田邊優貴子氏に紹介いただいた。
旅を重ね、極地を調査する研究者へ

南極というと、一般的には人を寄せつけぬ氷の大陸といったイメージ。だが、そこに点在する湖沼の底を覗いてみると、一面が緑で覆われた小宇宙のような生態系が存在する。こんな新鮮な驚きを与えてくれた今回のセミナー。講師は、水圏植物生理生態学を専門とする田邊優貴子氏。三度に及ぶ日本南極地域観測隊への参加や豊富な極地での調査歴を持つ田邊氏に、本講では南極や北極圏など極地の珍しい画像や動画をふんだんに用いながら、まだまだ知られていない南極の姿を紹介していただいた。
セミナー冒頭は講師の自己紹介から。そもそもなぜ極地を調査する研究者となったのか。「きっかけは小学校3年生のときに観たテレビ番組でした」という。アラスカやシベリアを紹介するその番組を見て、オーロラやそこで生きる動物の姿に感動した。そこで芽生えた「北への憧れ」が、長じてからは「旅」につながった。高校2年生の冬には「学校を休んで北海道のサロマ湖までキャンプに出かけた」。 3年生の夏は「利尻島までの野宿旅」。大学に入ると「水を得た魚のよう」に旅をした。ペルー、ボリビアの南米に始まり、ラオス、タイ、ミャンマーの東南アジア、そしてカナダ、ノルウェーへ。アフリカにも足を運んだ。念願だったアラスカには大学を1年間休学して行った。就職はせず研究者になるべく大学院に進学。アラスカへは在学中も2回出かけた。そうするうちに「実験室での研究よりも極地で自然を相手にした研究がしたい」と考えるようになり、それまでいた京都大学大学院を退学し、総合研究大学院大学へ転入。博士課程修了後は、国立極地研究所の研究員に。その後は東大勤務を経て、現在は早稲田大学の高等研究所に在籍。助教として極地での研究に取り組んでいる。
最初に田邊氏が見せてくれた画像は、ノルウェーのスヴァールバル諸島。ここは北極圏の野外調査のメッカであり、世界中から研究者が訪れる。飛行機で上空から見ると氷河だらけ。とても生き物などいそうに見えないが、「降り立つと大違い」だ。夏のツンドラは一面が花畑に覆われる。ここではトナカイやホッキョクギツネ、ホッキョクグマなどの哺乳類や、グース、パフィン、キョクアジサシといった鳥類の姿も多く見られる。
藻類や地衣類、バクテリアがつくるシンプルな南極の生態系

一方の南極は、大陸があるのが北極との大きな差だ。だが、そのほとんどは分厚い氷床で覆われている。大地が剥き出しになった露岩域は全体の2~3パーセント。寒い上に降水量は非常に少なく、乾燥している。言ってみれば「火星に近い気候」だ。そのなかで、オングル島にある日本の昭和基地周辺は露岩域が多く見られる貴重な場所。そこには今回のテーマである南極湖沼が点在している。
「南極で生き物というとペンギンとアザラシ。ペンギンはアデリーペンギンとコウテイペンギンの2種が暮らしています」
動画で見る動物たちは実に愛くるしい。陸上では天敵がほとんどいないため、人間を前にしても無防備で逆に興味を持って近づいて来るほどだ。他によく見られるのはアホウドリの仲間や小さなユキドリ、キョクアジサシ、オオトウゾクカモメなど。キョクアジサシは、北極からやって来る「世界でいちばん長距離を渡る鳥」。その移動距離は1年で約8万キロ、地球を約2周分というから驚きだ。
しかし、こうした動物たちは白夜の夏が終ると南極からは姿を消してしまう。エサも海に頼っている海洋生態系の動物であるため、陸上生態系の生き物であるとは言い難い。
では、氷で覆われた南極には陸上生態系の生物は存在しないのか。もちろん、そんなことはない。ごくシンプルながら、コケや藻類や地衣類、それより小さいバクテリアが南極特有の生態系をつくっている。
「生き物に必要なのは、炭素や窒素や燐などの栄養です。ところが、南極にはこれがほとんどありません」
それを提供してくれるのが動物の死骸だ。モニターに映ったのはアザラシの赤ちゃんのミイラ。まわりの地面には緑色の苔が生えている。こんなふうに、アザラシが死ぬとバクテリアがそれを分解して植物が生きることができる。ただし、南極ではそこに至るまでに時間がかかる。写真のアザラシの赤ちゃんのミイラは、年代分析をしてみたところ、約2000年前のものであると判明した。バクテリアの活動が低い南極では、物が腐らないのである。
もうひとつ、南極には植物が繁茂できる場所がある。それが露岩域にある湖沼だ。昭和基地周辺の湖沼の数は約100。2万年前の最終氷河期の終わりとともにできたこれらの湖には、塩分濃度の高い塩湖もあれば淡水の湖もある。透明なものや土が流れこんで乳白色になったものなど、それぞれ色も水質も違うという。
南極湖沼は、一つひとつが生命の進化を教えてくれる「小宇宙」

田邊氏が調査対象としているのは湖底に藻類が生息している淡水の湖。水中に潜ってみると、陸上とはまったく違う世界。湖底一面が草原状になっていて、そこには円柱状だったり、突起状だったりと、藻類やコケでできた「コケボウズ」が無数に存在する。大きなものだと高さ80センチに達するこの「コケボウズ」は、数十種類のコケと藻類とシアノバクテリアが共存する集合体だ。シアノバクテリアとは、地球上で初めて酸素を生み出す光合成を行なった生命と言われている。藻類はそれが進化したものだ。一つひとつは顕微鏡サイズのこのシアノバクテリアがつくる「コケボウズ」は、あたかもひとつの生物に見える。これが湖底一面を覆い尽くしている様は圧巻であり、なんともいえない不思議な感動を与えてくれる。
湖底に藻類たちが繁茂している理由のひとつは水温の高さ。外がマイナス40度の冬でも湖底の水温は4度ほど。夏は10度まで上昇することもある。必要な栄養素はシアノバクテリアが空中から窒素を取り込むことで確保。強烈な紫外線はそれに抗する色素を持つことで防いでいる。サンプルを取って内部の栄養素を調べてみると、「富栄養湖である宍道湖よりも栄養分が高かった」。この「コケボウズ」の形状は湖によってさまざま。こうした生態系を持つ湖沼は一つひとつが「小宇宙」だ。田邊氏はここを生命の起源や進化を考える上で「ガラパゴス諸島をしのぐ場所」だと捉えている。
情報通信が発達した現在は国内にいても研究ができる時代。が、行ってみなければわからないことはたくさんある。田邊氏の「夢」は、「動けるまで極地で調査をして、おもしろいことを発見して世の中に伝えていく」こと。3日後にはカナダに旅立つという気鋭の研究者のセミナーは、盛大な拍手で幕を閉じた。
講師紹介
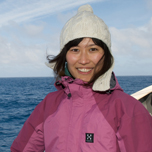
- 田邊 優貴子(たなべ ゆきこ)
- 早稲田大学 高等研究所 助教
1978年青森市生まれ。植物生理生態学者。博士(理学)。2006年、京都大学大学院博士課程退学後、2008年、総合研究大学院大学博士課程修了。国立極地研究所・研究員、東京大学・日本学術振興会特別研究員を経て、現職。小学生の頃、テレビで偶然目にした極北の地に憧れを抱く。大学4年の時、真冬のアラスカ・ブルックス山脈麓のエスキモーの村で過ごし、その思いは揺るがぬものとなる。バックパッカーとして世界を旅したが、人間が暮らしている場所と同じ地球上とは思えない圧倒的な自然と、そこに暮らす生き物の姿に魅せられ、極地をフィールドにした研究者となる。研究のかたわら、地球やそこに息づく生命の素晴らしさを伝えるべく講演や執筆活動を行っている。第49次(2007-2008)、第51次(2009-2010)、第53次(2011-2012)の3度の日本南極地域観測隊に参加。その他、北極・スヴァールバル諸島、ウガンダ・ルウェンゾリ山地など、極地を舞台にした野外調査歴を持つ。ナショナルジオグラフィックWeb版にて「南極なう!」連載。著書に「すてきな地球の果て」(ポプラ社)がある。