イベントレポート
2014年2月13日(木)19:00~21:00
池上 英洋(いけがみ ひでひろ) / 芸術史家・東京造形大学准教授
中世ヨーロッパの暮らしを覗く
中世ヨーロッパを生きた人々は、実際にどのような生活をおくっていたのだろう。彼らはなにを食べて、どこで寝て、どんな仕事をしていたのか。どのような恋をして、結婚をし、家庭を作って、いかに育児していたのか。彼らは日々、何におびえ、何に苦しみ、何に笑っていたのか。このセミナーでは、残された多くの絵画や版画、都市や建築物といった文化の産物を「窓」として使いながら、昔の人々の生活ぶりと一生を、一緒に覗いていった。一部の英雄ではない、ごく普通の人々の暮らしを知り、そして当時の社会の仕組みを知っていくうちに、西洋の文化そのものに対する理解も深まり、皆さまの今後の美術鑑賞や観光旅行が一層味わい深いものとなっていくはずである。
絵画には描かれる動機がある

教壇に立つ東京造形大学では美術史と文化史を担当。「基本的には美しい美術品を扱っている」という池上英洋氏。ただ一方で、「絵画というものは決してきれいなものだけが残されているわけではない」という。
「識字率の低い時代、絵画は文字よりも優れた、情報を伝える最大のメディアでした」
一般庶民は、絵画から知識や情報を得、ときには絵画を教科書として使っていた。そこには見ていて「醜いもの」や「痛いもの」もある。当時の人々の生活を知りければ、そうした絵画に触れるといい。今回のセミナーでは多数の図版を見ながら、タイトル通り、中世ヨーロッパの暮らしを覗いてみた。
「いかなる絵画にも描かれる動機がある」と池上氏。見せてくれた最初の1枚は、修道会での埋葬シーンを描いたもの。手前には棺に死者を収める修道士。奥にはペストによって瀕死状態となっている患者。死者はもちろん、生者である修道士たちの顔も青白く、全体に美しい作品とは言い難い。
なぜこんな絵が描かれたのか。そこには「神へのアピール」という動機がある。14世紀にヨーロッパ全土で大流行したペスト=黒死病は、男女問わず当時の死因第1位のおそろしい病気だった。感染の恐怖から、人々は患者が死ぬときちんとした埋葬をせずに捨てるように処理していた。しかし、この修道会ではこうして埋葬シーンを絵画に残すことで、自分たちが恐怖を乗り越え、きちんと死者をキリスト教の教えに従い、土葬していたことをアピールした。いわば「自画自賛」の1枚。こんなふうに、すべての絵画には意味があるという。
病気、出産……当時の医療がわかる絵画の数々
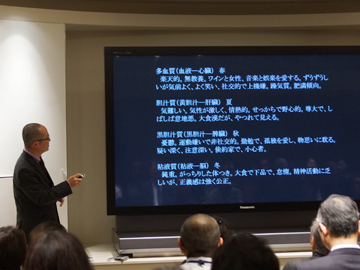
当時の人々にとって最大の関心事は「死」。残された絵画を見れば、人々が病をどう理解していたかや医療技術などがわかる。死者や病人が描かれた作品によく登場するのは悪魔。病原菌などというものの存在を知らないこの時代、ペストやマラリア、癩病などの感染症は、人間に対する神の何らかの罰か、悪霊や悪魔の仕業だと考えられていたことがどの絵からも読み取れる。むろん、人間もそれに対抗手段を講じる。それが医療だが、中世ヨーロッパの医学は、その知識も技術も基本的に2000年前の古代ギリシア時代からさして進歩していない。病の診断は採尿が中心で、治療は瀉血(しゃけつ)。外科治療や中国から伝わったツボ治療などもあるにはあったものの、現代の医療と比べると肌寒くなるようなレベルだった。それでも病気になって医師に診てもらえるのならまだいい方。それができるのはごく一部の富裕層に限られていた。医師は全員が大学卒。数はけっして多くはなく、バロック時代のパリですら、30万人の人口に対し医師は85人しかいなかったという記録が残されている。
ここでは、その頃の医療を描いた絵を何枚か鑑賞。中世ヨーロッパの絵画は「下手巧なかわいらしい絵画」が多いが、そこに描かれているシーンはなかなか壮絶だ。縫合のない時代の焼き鏝(やきごて)による止血や、大量の出血をともなう脱肛の処置、ドリルを使った頭蓋骨穿孔手術、牛の胃袋や膀胱を使った浣腸、麻酔のない時代の足の切断……どれを見ても勘弁願いたいようなものばかりだ。
「病は今よりももっと、想像がつかないほどおそろしいものだった。これらの絵画に触れると、我々がどれだけ医学の恩恵に授かっているかがわかりますね」
大変なのは病気だけではない。出産もまた命がけだった。この時代、ペストに次ぐ女性の死因の第2位は産褥熱(さんじょくねつ)。女性の月経や出産を「穢(けが)れたもの」とする性モラルによって、出産だけは医師の手によらず産婆に頼っていたこともあり、当時は難産や産褥熱で亡くなる女性が後を絶たなかった。帝王切開は「死」を意味し、母体が助からないと判断された場合のみ行われた。そのシーンを描いた残酷な絵画も残っている。こうして助け出された新生児も乳母がいなければ生きてはいけない。また、ろくに避妊薬などない時代だったため、望まない子を出産する女性も少なくなかった。そうした不幸な子どもたちを救済すべく「捨て子養育院」が設けられていた。そこには今で言う「赤ちゃんポスト」があり、新生児たちに乳をやる乳母がいた。「カリタス」という絵画には、子どもたちに母乳を与える美しい女性の姿が描かれている。女性が乳母であることは、彼女の髪の色と乳を吸う子どもの髪の色が違うことから容易に推察できる。池上氏いわく「その時代の社会状況を知っていれば、絵画はより深く理解できます」。
「美術鑑賞をなさる際には、そうした視点を持つといいでしょうね」
絵を見れば一目瞭然。都市部と農村部の結婚の違い

セミナーの最後は「都市の結婚」と「農村の結婚」を比較。都市の結婚が親によって決められた一種の政略結婚であることが多いのに対し、農村の結婚は人手=労働力を増やすことを第一義とした男女の「出会いの場」であった。性的に自由な農村に比べ、都市の結婚は初夜に結婚という契約がきちんと履行されるかどうか立会人がつく。同じ時代でも都市と農村では考え方に大きな違いがあったことがわかる。また、都市部の結婚には多額の持参金が必要だったこともいくつかの絵画が示している。絵画で描かれた指示書には、ベッドやシーツ、指輪、絨毯、紐類など、女性が持参すべき品々が並んでいる。ちなみに当時のヨーロッパの都市部は徒弟制度のギルド社会。男性はある程度歳を重ねなければ結婚ができなかった。他方、女性は16歳程度での嫁入りが当たり前。このため年の離れた夫婦が多かった。ラストの1枚は、そんな歪んだ社会を揶揄した作品。亡くなる直前の夫を見て泣いている若い妻。だが、その手は横にいる若い愛人の手とつながっている。どんな時代でも女性はしたたか。諷刺のきいた絵画は、見る人を笑いに誘ったに違いない。
仕事柄、学生と美術館によく行くという池上氏。「夢」は「美術鑑賞の形態を変えてゆく」ことだ。日本の美術館は作品を前に話をしていると係員に「しっ、と指でやられる」。だが、欧米の美術館では小学生が絵画の前で車座に座って絵画について議論している。まわりの大人たちはそれを微笑ましく見ている。
「美術品はあがめるものではなく身近なもの。そう考えれば鑑賞形態も変わると思います」
講師紹介

- 池上 英洋(いけがみ ひでひろ)
- 芸術史家・東京造形大学准教授
1967年広島県生れ。東京藝術大学卒業、同大学院修士課程修了。専門はイタリアを中心とした西洋美術史・文化史。NHKラジオのイタリア語講座応用編の講師も経験。著書に『Due Volti dell‘Anamorfosi』(Clueb、イタリア)、『レオナルド・ダ・ヴィンチ―西洋絵画の巨匠8』(小学館)、『イタリア24の都市の物語』『ルネサンス歴史と芸術の物語』『ルネサンス三巨匠の物語』(いずれも光文社新書)、『西洋美術史入門』(ちくまプリマー新書)、『神のごときミケランジェロ』(新潮社とんぼの本)などがある。


