イベントレポート
2015年7月23日(木)19:00~21:00
佐竹 晃太(さたけ こうた) / 株式会社キュア・アップ(CureApp, Inc.)代表取締役社長・呼吸器内科医
「モバイルヘルス」で変わる日本の医療
~スマートフォンアプリであなたの病気がよくなる時代へ~
昨年秋に薬事法が改正され、医療用ソフトウェアが薬事規制と承認の対象となった。これによって、国内の臨床現場では、今までにはない医療用アプリケーションが次々と導入されることが期待されている。一方、アメリカなどの海外では、モバイルアプリケーションを活用した診療や治療がすでに導入されている事例があるのだ。今回のセミナーは、ジョンズ・ホプキンス大学院で医療情報科学の研究に従事していた医師の佐竹晃太氏に、海外における医療用ソフトウェアの現状についてお話しいただいた。日本の医療におけるソフトウェアが果たせる役割について考える機会となった。
ITによって変わってゆく医療現場

「今日はモバイルヘルスという新しい領域の話をさせていただきたいと思います」
モバイルヘルスとは、簡単に言うと「スマートフォンを用いた医療」のこと。病気というとこれまでは薬や医療機器による手術で治すのが当たり前。それをスマートフォンの専用アプリケーションを使って治したり病状を改善させようというのがモバイルヘルスだ。講師の佐竹晃太氏はその医療用アプリケーションを開発するベンチャー企業『キュア・アップ(CureApp, Inc.)』の代表。もともとは病院の呼吸器内科に勤務する「お医者さん」だった佐竹氏が、どうしてベンチャー企業を立ち上げて医療用アプリを手がけるようになったのか。背景には医療従事者が抱え持つ問題意識とアメリカ留学中に受けた「衝撃」があったという。
佐竹氏が前職の日本赤十字社医療センターに勤務していたのは3年間。その後、「医療現場以外のことも知りたい」と中国にMBA留学。ここで経営について学んだあと、医療系の大学院としては有名なアメリカのジョンズ・ホプキンス大学院へと留学した。専攻したのは「公衆衛生学」と「医療インフォマティクス」。前者は医療を患者と一対一の診療現場だけではなく「マス」で見ようというもの。後者はというと「まだ日本では聞き慣れない言葉」。「ITを医療現場に取り入れたときにそこで起こる現象をアカデミックに評価しましょうという学問」だという。
「例えば、今まで紙のカルテだったものを電子カルテに変えたら医療ミスが減るのかとか、EHRという病院間での電子カルテの情報共有だとか。日本ではDNA解析などのバイオインフォマティクスが注目されていますが、これも医療インフォマティクスの一部になります」
医療インフォマティクスを構成するのは「バイオインフォマティクス」の他、CTやMRIなどの画像を解析する「イメージインフォマティクス」、マスの目で見た「パブリックヘルスインフォマティクス」、病院の診療現場で使われる「クリニカルインフォマティクス」の4つ。「まだまだアカデミアの中では有名なジャンルではない」というが、最近は論文も多く発表され医学界でも注目されつつあるという。アメリカではすでにたくさんの医療用ソフトウェアが開発され、アプリだけでも100個以上が承認されている。この流れに合わせて日本でも昨年、薬事法を改正。今までは薬や医療機器に限定されていた規制や承認の対象がソフトウェアにも適用されるようになった。
薬より効くスマートフォンアプリ
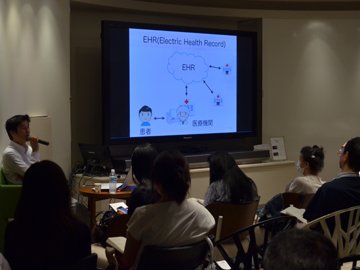
佐竹氏が「衝撃」を受けたのはジョンズ・ホプキンス大学院でこの医療インフォマティクスを学んでいるとき。インターン先にどうかと教授にすすめられたWellDoc社の開発した「糖尿病治療アプリ」についての論文を読んで衝撃を受けた。そこにあったのは、このアプリを使用した臨床試験のデータ。
「見ると、このアプリを使った人は血糖状態を示すへモグロビンA1cが使用してない人と比較して、1.2も下がっていました。薬の場合はこれが平均して0.9くらいですから、そんじょそこらの薬を飲むよりも効果があるんですね」
アプリは糖尿病専門医だったWellDoc社の創業者が「自分で数値を記録するのに携帯が使えると便利」という患者の声をきっかけに開発したもの。それが「やっていくうちに入力した数値にフィードバックを与えるような機能がどんどんついていき」、ついには今のようなものができたという。
「イメージ的にはスマートフォンがミニドクターになっていると思ってくださればいい。このアプリに患者さんが血糖値や食事量、運動量などを入力すると、システムの方で独自のアルゴリズムが組まれていて、まるでお医者さんが頭の中で考えたような形で〈今日のあなたの状態からすると、食事はこうしましょう〉と教えてくれるんです」
言ってみれば毎日病院で診療を受けているようなもの。内科医目線でこれを見たとき、「これまで自分がやってきたことは何だったのだろうと思った」。内科医にとって「病気を治す」とは「薬を飲んでもらうこと」。それが薬を飲まずにアプリと毎日向き合うだけでよくなってしまう。しかも開発費は日本円で数千万から数億円。新薬の開発が数百億円から数千億円もかかるということを考えれば、これは「高騰する医療費のソリューションそのもの」だとも思えた。
「日本の医療費は年間40兆円。医療従事者はみんな危機的状況だと問題意識を持っています。でも何をしていいかわからない。僕もそうでした。だけど、このアプリなら新薬を開発する100分の1のコストで済む。これはもう、やらない理由がないですよね」
病気によっては「薬のかわりにアプリが処方される」時代に

アメリカから帰国したのが昨年の6月。7月にはキュア・アップ(CureApp, Inc.)を設立した。慶應義塾大学病院と共同開発しているアプリの第一弾は「呼吸器内科の医師としてずっと気になっていたニコチン依存症の治療」を目的としたもの。目指すは日本初となる「薬事法での承認」だ。こうしたいわゆる「デジタルヘルス」には健康な人の病気予防などを目的とした「健康ウェルネス系」と「医療系」があるが、まだまだ「医療系」は少ないのが現状。しかし、これからは佐竹氏が目指しているような「病気をよくする」ための医療用アプリケーションが増えることが期待されている。対象となる病気の「候補」はミニドクターであるアプリによる毎日のコーチングや心理療法の効果が期待できるもの。具体的には「生活習慣病」や「精神疾患」などが挙げられるという。何より嬉しいのは「薬と違って副作用がないところ」と「医療費が抑えられる」点だ。
セミナーではこの他にも先行する海外の事例を紹介。眼底検査や皮膚がんの検査、心筋梗塞後のリハビリ用アプリ、ゲームを使ったうつ病治療プログラムなど、さまざまな取り組みを見てみた。
可能性に満ちたモバイルヘルス。ただし高齢者にはスマートフォンを持っていない人も多い。鍵は「診療現場に組み込むこと」だ。
「普及させるにはアプリ単独で使ってもらうより医師からのすすめなど何かしらのオペレーションの中にアプリを組み込むこと。そうすることで信頼度が高くなります」
佐竹氏の「夢」は「3年後、5年後、みなさんが病院に行ったときにお医者さんが薬のかわりにアプリを処方するようになること。スマートフォンアプリを使うと病気がよくなる。そういった世界をつくりたいと思っています」
講師紹介

- 佐竹 晃太(さたけ こうた)
- 株式会社キュア・アップ(CureApp, Inc.)代表取締役社長・呼吸器内科医
1982年生まれ。慶應義塾大学医学部卒業。日本赤十字社医療センターなどで呼吸器内科医として診療に従事。その後、上海ビジネススクールCEIBSにてMBAを取得し、米国ジョンズ・ホプキンス大学院にて医療情報科学を研究。帰国後、2014年に株式会社キュア・アップ(CureApp, Inc.)を創業。「アプリで病気を治療する未来を創造する」というヴィジョンのもと、日本初となる疾患治療用アプリケーションの臨床応用および事業化を進めている。現在、『日経テクノロジーオンライン』で、「医師・佐竹晃太の『モバイルヘルス』で変わる医療」を連載中。


